
宮口精二
本名・宮口精次(みやぐちせいじ)
1913
年(大正2年) 11月15日・東京市本所区緑町生まれ。
大工の父(周市)と母(もと)の二男として生まれる。
幼児期に同じ本所区内の林町に移転。関東大震災で母、祖父、祖母、弟と死別。
中和尋常小学校から26年に東京市立第二中学(現・都立上野高校)に入学するが、
学資が続かず1学期が終わったところで、同校の夜間部である上野夜間中学へ転じる。
同時に校長の紹介で福徳生命東京支店に給仕として入社。給仕をしながら夜間部に通う。
1931
年 卒業。給仕として勤める。本郷座で見た新劇に感動
「同じ貧乏するなら、自分の好きな道で」と1933
年 9月 築地座の研究生となる。1934
年 1月 「アルトハイデルベルヒ」の通行人の学生役で初舞台。1935
年 2月 「釣堀にて」で中村伸郎の代役として立ち、一言だが初めてセリフのある役で出演。1937
年 9月 文学座の結成に杉村春子らと共に参加。 1940年 6月25日封切りの「奥村五百子」で映画デビュー?「当時私は築地小劇場で芝居をしてましたが、その前に杉村春子さんが豊田四郎さんの監督で『奥村五百子伝』というものに出たんです。戦争に突入した時分ですから、そういう戦意高揚の映画をそろそろ創り始めた頃でした。杉村さんが主役で出演するんで、私はその頃ペーペーでしたが、「宮口さん映画に馴れておくのも良いでしょう」というわけで、私までがほんの仕出しで出ることになりました。園遊会にでるだけのセリフも何もない役でしたが、それに駆り出されたんです。」
1944
年 文学座の移動演劇「太平洋の風」公演中に徴用令が来たが軍事保護院の尽力によって延期された。1945
年 5月5日 中村伸郎と共に石川県小松市に集団疎開第一陣として疎開。黒澤明監督の「續姿三四郎」に出演。(初めてセリフのある役)
「その時は今ひとつ映画に乗り気でなかった森さん(森雅之)が出演を断っちゃってね。僕は本当は出演したかったの。貧乏でピーピーして、お金も欲しかったから。だけど、大先輩の森さんをさしおいて「僕だけ出ます!」ってわけにはいかないやね。」
太平洋戦争末期は文学座の移動演劇隊に加わり、北陸地方を巡演。
公演先で終戦を迎える。
1949
年 文学座公演「あきくさばなし」「女の一生」「雲の涯」等で第一回毎日演劇賞受賞。1954
年 「七人の侍」の久蔵役で毎日映画コンクール男優助演賞受賞。1957
年 日中の演劇交流を図る調印式の為に訪中する日本側の一行に書記として随行。 1960年 新劇合同演劇で北京などを巡回1965
年 2月8日 文学座を退団。5月 東宝演劇部に1年ごとの契約で入り、東宝現代劇など数多くに出演。
1970
年 9月 季刊雑誌『俳優館』創刊。(86年まで16年間、41冊発行)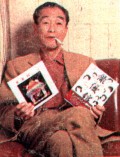
1976
年 10月15日 白川書院より『俳優館 宮口精二<対談>』刊行。1983
年 5月31日 大和山出版社より『俳優館 宮口精二対談集』刊行。11月 紫綬褒章受章。
1984
年 10月 東京・帝国劇場で最後の舞台「桜の園」。12月5日 国立東京第二病院に入院。
1985
年 4月12日 午後11時30分、肺ガンのため東京都目黒区の国立東京第二病院にて、死去。享年71歳。4月13日
このプロフィールは『日本映画人名事典〜男優篇〜』
(キネマ旬報社)、『巨匠のメチエ』(フィルムアート社)、『役者という存在・宮口精二について』(軌跡社)、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞、週刊平凡、女性セブン、俳優館、キネマ旬報1985年6月上旬号を基に作成いたしました。上記文中敬称略。 もどる